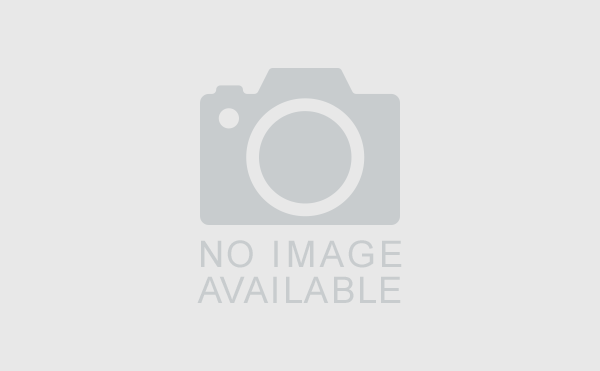公正証書遺言を作った後の注意点
先日、ある方の公正証書遺言を作りに公証役場に行きました。
そのとき担当していただいた公証人が言っていた注意点が印象に残りました。
以下、その点を説明します。
なお、正式には「公正証書遺言」ではなく「遺言公正証書」ですが、「公正証書遺言」の方が一般用語として定着している感がありますので、以下でも「公正証書遺言」と表記します。
目次
公正証書遺言の謄本は封印しない
公正証書遺言を作ると、原本は公証役場で保管されます。
遺言を作った人には、原本と同じものということで「謄本」が渡されます。
通常、公正証書遺言の謄本と封筒を渡されるのですが、公証人は、
「封筒に入れて、封印をしないようにしてください。」
と注意していました。
法律専門家でなければ、何のことかよく分からないと思います。
民法1004条3項に、次のような規定があります。
”封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。”
これには5万円以下の過料に処するという制裁もあります。
公正証書遺言のメリットに「検認」がいらないという点があります。
自宅で自筆証書遺言が見つかった場合には、裁判所で遺言書を確認する手続をしなければなりません。
これを「検認」といいます。
公正証書遺言の場合は、この検認の手続が不要です。
ところが、中身が公正証書遺言だとしても、封筒に入れてそれに封印をしてしまうと、
「封印のある遺言書」として検認が必要となってしまうので、
そのようなことがないよう、封印はしないように公証人は注意していました。
公正証書遺言の謄本に押印しない
公正証書遺言を作るときには、遺言を作る方と証人2名が署名・押印します。
これは、公正証書遺言の原本に署名・押印をします。謄本には署名・押印をしません。
謄本には、私が証人になった場合には、「永井敦史 ㊞」というのが記載してあります。
これは、原本には、永井敦史という署名と押印があることを意味しています。
ところが、この「㊞」に必要がないのに、印鑑を押した方がいたそうで、公証人は、
「㊞のところに、印鑑は押さないでください。」と言っていました。
確かに、普通は「㊞」とあったら、そこに印鑑を押すべきと思ってしまいますからね・・・
まとめ
公証人が注意していたことは、これまで意識したことがなかったので、紹介しました。